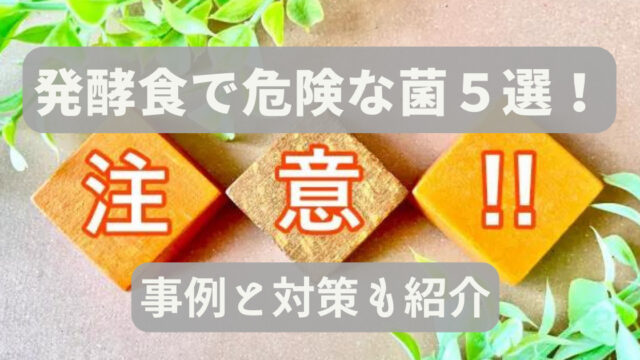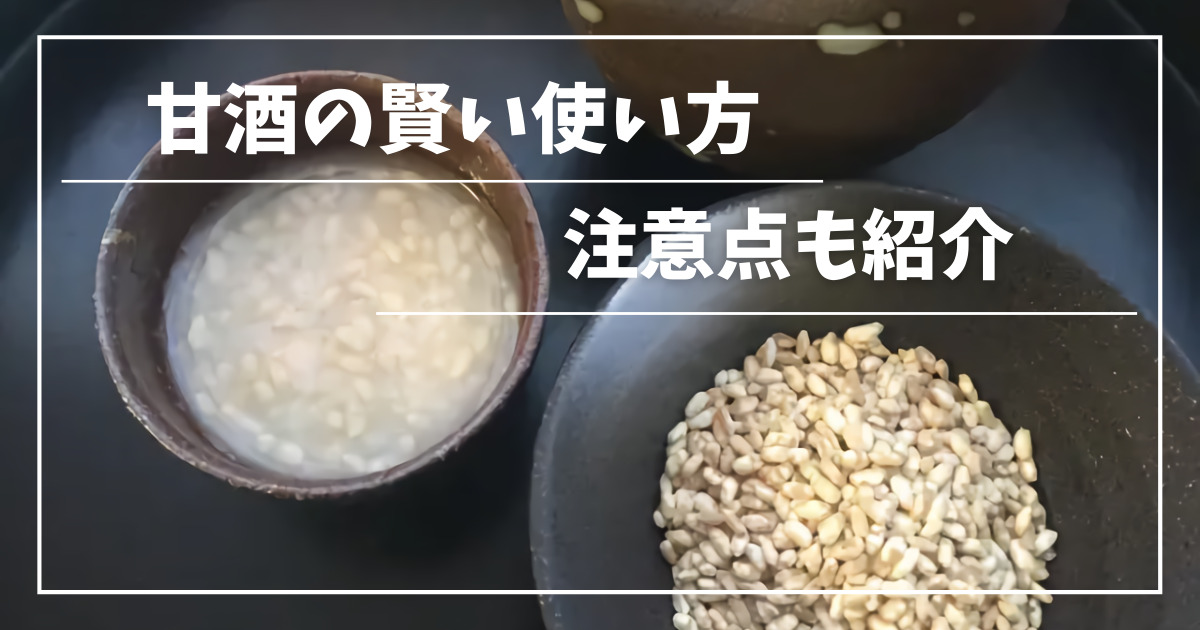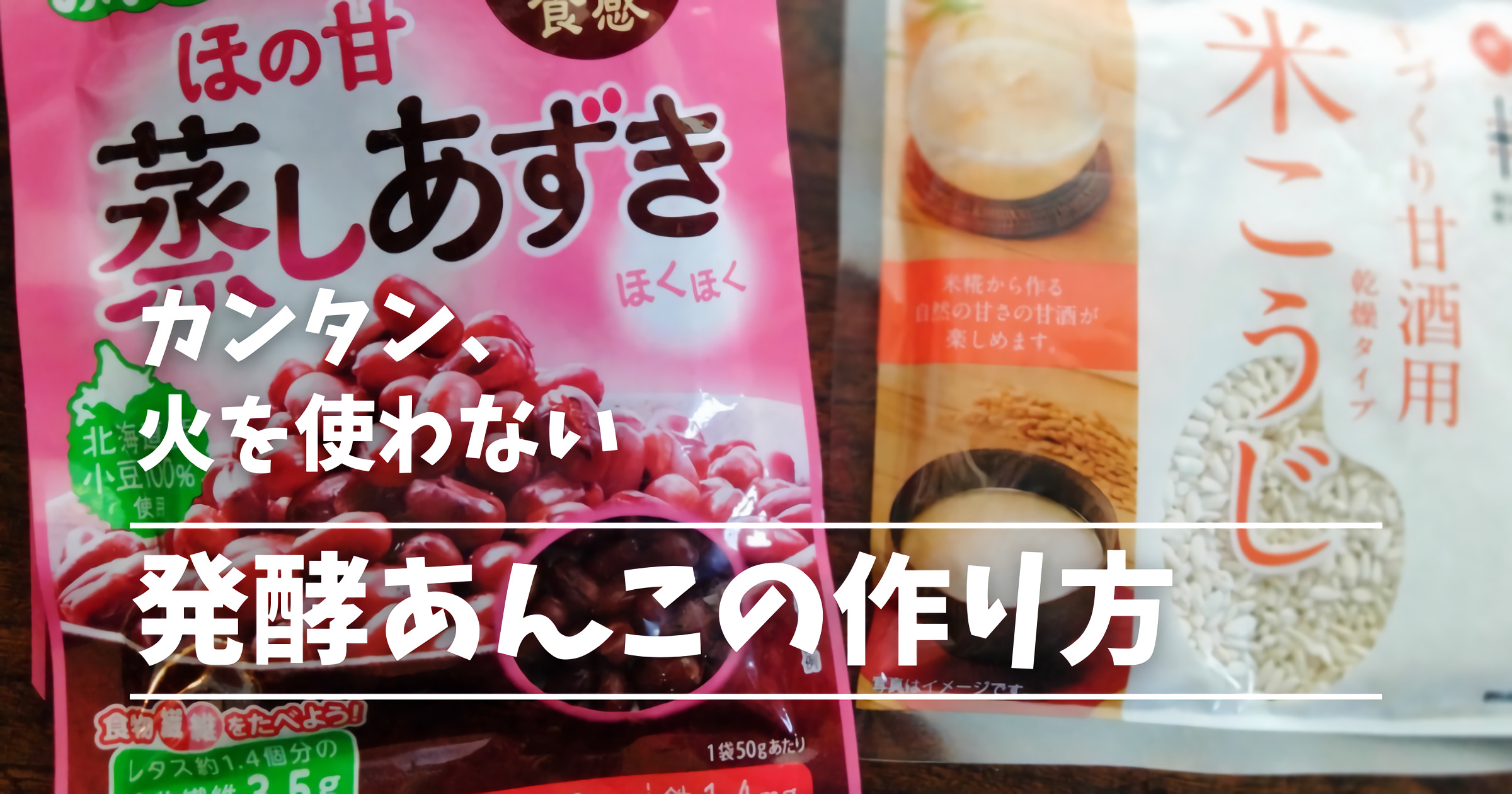【漬物桶不要】甘酒でキムチが作れる?甘酒を使った自家製キムチの作り方

自家製キムチは意外と簡単に作れます。
市販のキムチには添加物を使用してるものが多く、塩と唐辛子だけで漬けたシンプルなものって中々ありませんよね。
なので、手作りできるようになると
無添加キムチがいつでも気軽に楽しめます。
キムチはまずヤンニョム(キムチの素)を作ります。
その後、塩漬けにした野菜を漬ける本漬けに入ります。
キムチの素であるヤンニョムには
キムチのりと呼ばれるペーストを入れて乳酸菌発酵を促しますが、じつはキムチのりには麹の甘酒が使えます。
この記事では家庭でも簡単に作れる
甘酒キムチの漬け方を紹介いたします。
さらに、
- 塩漬けの手間を半減
- 漬物桶がいらない
といったより手軽に仕込むコツも紹介します。

甘酒を使って漬けたキムチ
- 初めてキムチを作る方
- 甘酒レパートリーを増やしたい方
- 手軽にキムチを仕込んでみたい方
▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼
甘酒キムチとは

甘酒キムチとは、韓国の伝統発酵食・キムチに日本の発酵食である甘酒を使用したものです。
キムチには植物性乳酸菌により爽やかな酸味が出ますが、甘酒がこの植物性乳酸菌の繁殖を助ける栄養源として使われます。
甘酒キムチの基本的な作り方
通常のキムチと甘酒キムチの作り方に大きな違いはありません。
通常のキムチは
この時、甘酒を入れる
冷蔵庫か冷暗所にて2週間くらい熟成
と、全体で見るとステップは3つだけのシンプルなものです。
甘酒キムチの食べ方と合わせる料理
完成して甘酒キムチは通常のものよりも甘酒が効いて、唐辛子の辛味の中にほのかな甘さを感じされる優しい味わいに仕上がります。
通常のキムチと同様にそのまま食べたり、キムチ鍋にしたりはもちろん、チャーハンやサラダなど幅広くお使いいただけます。
キムチの素(ヤンニョム)の作り方

手作りキムチはキムチの素となるヤンニョムを作るところから始まります。
- 唐辛子粉 200g
- 甘酒の素(キムチのり) 90g
- おろしにんにく 30g
- おろししょうが 50g
- おろし玉ねぎ 半玉分
- おろしリンゴ 一玉分
- 人参(千切り) 一本分
- ニラ もしくは 青ネギ 1束
- ナンプラー 50cc
- 白ごま 適量
- 出汁汁 (水300cc、昆布5×5cm程度、煮干し10g、鰹節5g)
このヤンニョムを元にして、漬けこむ野菜によってキムチの名前が変化します。

出汁をとる
はじめに出汁をとります。
煮干しの頭とワタを取り除きましょう。

頭のすぐ下に収まってるのがワタですね。
苦みの元なので取り除きます。
次に鰹節・昆布・水を加え、沸騰したら火を止めて、冷めるまで置きます。

甘酒をキムチのりの代用として使う
ヤンニョムにはキムチのりというのが必要です。
キムチのりとは、餅米や小麦粉を水でのばしたもの。
でんぷんのとろみによるつなぎとしての効果に加え、キムチ特有の酸味を生む乳酸菌の栄養源になります。

日本酒もお米のでんぷんから菌達の栄養源が生み出されるので、シンパシーを感じます。
そこで今回は、このキムチのりに甘酒を利用します。

本家のキムチのり同様に穀物由来ですので違和感なく使えて、甘酒の優しい甘さでより食べやすく感じます。
市販の甘酒を使用する場合は、濃縮タイプを使ってください。

野菜を刻む・すりおろす

まずは人参とニラ(もしくは青ネギ)を食べやすい大きさ(5mm程度の短冊切り)に刻みます。
ピーラーやスライサーを使うと薄く切れますが、くれぐれもケガにご注意ください。
次ににんにく・しょうが・玉ねぎ・りんごの球状のものをすりおろします。
以上が終われば、全ての材料を混ぜ合わせます。
これでヤンニョムの完成です。
キムチの本漬け

ここからは白菜と合わせて、キムチを仕込みます。
- 白菜 1玉
- 水 1200cc
- 塩 150g
- キムチの素 上記参照
白菜を先に刻み、塩水に浸ける
材料の水と塩を合わせて、塩水を作ったら、食べやすい大きさに切った白菜を30分浸けます。

立て塩で手間を半減
先に白菜を刻んでから塩漬けにしましょう。
こうすることで、白菜の一枚一枚に塩をすり込む手間を半減しつつ、塩漬けのムラも無くなります。

塩水に浸けて塩を振るのを立て塩と呼びます。
水気を切って一晩置く
30分経ったら、ザルにあけて水気を切ります。

水気はしっかり切りたいのでラップを上にかけて、軽く重石をして一晩置きます。
一晩経ったら白菜とキムチの素と合わせてキムチの完成です。
漬物桶がいらない

そして、ジップロックなどのフリーザーパックで冷蔵保存します。
こうすると冷蔵庫にも入れやすいのがメリット。
冷蔵庫で2週間くらい経ってからが食べ頃です。
酸味が立ちすぎる前、2~3週間程度で食べきりましょう。

漬けた直後の若いキムチでも、ごま油をたらして食べてみてください。
白菜がパリパリでまた違ったおいしさがありますよ。
まとめ:甘酒でやさしい味わいのキムチが作れる!

ちょっと手間はかかりますが、白菜が瑞々しくて市販のものとはまた違った味わいが楽しめます。
冬に白菜がたくさん穫れた、頂いたという時の保存方法としてもいいですね。
このブログは手作り発酵食を作り方を紹介してるブログ
当ブログでは麹を中心とした発酵食の作り方を紹介しております。

ご自宅でも思ったより簡単にできますが、安全に発酵食を楽しむにはいくつかの注意点もあります。
そんなことについても紹介してますので、ぜひ合わせて参考にしてみてください▼