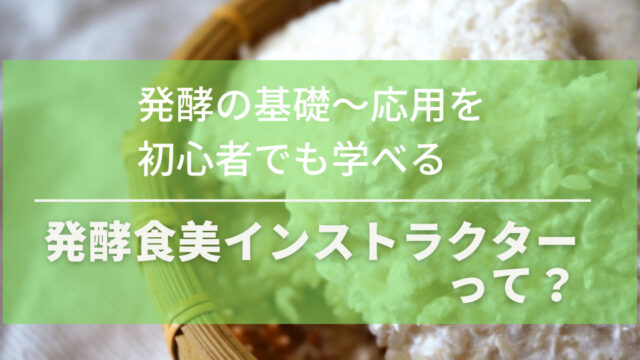酒蔵の求人はどうやって探す?蔵人がおすすめの探し方3選

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼
私が蔵人になったのは約10年前です。
その頃は今よりも情報が少なく、情報を入手するのに割と苦労しました。
というのも
酒蔵の多くが社員100人未満の中小企業です。
人員募集も1~2人がほとんどで
マイナビやリクナビなどの一括採用の大手新卒就活サイトに掲載されることはほぼありません。
そして
今現在も情報が多いとは決して言えません。
酒蔵に勤めたいと思ったら
情報をどうやって入手するかがとても重要です。
酒蔵に限らず、募集要項と勤務実態にズレがあるなんてよくある話ですよね。
「思っていた仕事と違う…」
なんてミスマッチは絶対に避けるべきです。
そこでこの記事では、
- 蔵人とはどんな仕事?
- 酒蔵の求人の探し方
について今も酒蔵に勤める蔵人が紹介します。
どの業界も人材育成に苦心している昨今
酒蔵側と働き手側のミスマッチを避けるためにもキレイごとは抜きにしてお伝えしますので、興味のある人はぜひ参考にしてみてくださいね。
蔵人とはどんな仕事?

まずは蔵人とはどんな仕事なのかを紹介します。
ざっくりいうと発酵食の製造に携わる人
蔵人とは
- 酒造業
(日本酒・焼酎・みりん等) - 味噌
- 醤油
など、日本の発酵食製造に携わる人達のことを指します。
共通点としてどれも麹を使う発酵食です。
これらの製造所はいわゆる蔵構えの建物で製造されてきたことから、蔵に勤める人という意味で蔵人と呼ばれています。

この記事では
日本酒の蔵人をメインに話を進めていきます。
日本酒以外の発酵食に興味ある人は
こちらもどうぞ↓


杜氏は蔵人?蔵人の役職について
実は蔵人にも役職があります。
例えば麹を担当する蔵人を麹屋(こうじや)、蒸し釜の担当を釜屋(かまや)といった具合に、役割によって様々な肩書きが存在します。
そんな酒蔵の蔵人全体を統括する
責任者のことを杜氏(とうじ)といいます。
蔵人が酒造従事者全体を指す言葉に対して、杜氏は蔵人のリーダーを指す言葉です。

杜氏ってじつは役職で、「部長」とか「専務」っていうのに近いイメージです。
蔵人の雇用形態は2つ

蔵人の雇用形態はちょっと特殊です。
大きくわけて
- 季節雇用
…酒造期だけ蔵人として働く - 通年雇用
…年間を通じて働く
があります。
順に紹介していきますね。
①:季節雇用
働いた分季節雇用の蔵人は
主に10月頃~3月頃までの冬季だけ働き、働いた分の日給(もしくは月給)を報酬として受け取ります。
歴史的に見ても蔵人の季節雇用は古くから存在してる雇用形態です。
その理由は2つあります↓
日本酒は冬に1年分作る
日本酒は雑菌からの汚染を防ぐため
低くて6~8℃の低温で仕込みます。
そのため、その温度まで熱々に蒸された米を冷やす必要があるため、外気が冷たい冬がもっともお酒造りに適しています。
これを寒仕込みといい、1年分のお酒を冬に集中して製造する、今も多くの酒蔵で採用されてる方法です。
そのため人手の欲しい冬にだけ季節雇用というかたちで働いてきた背景があります。
閑散期の農家の出稼ぎ
先述の寒仕込みには欠点がひとつあり、それは冬しかお酒が仕込めないという点です。
また、酒蔵としても冬の繁忙期にだけ人を雇えれば人件費が浮きます。
そこで農業や林業など冬に閑散期を迎える人達が酒蔵へと出稼ぎに出るようになりました。
そうした需要と供給の一致もあり
季節雇用が広く浸透して、今でも多くの酒蔵で続けられています。
②:通年雇用
一方で、
・人材育成
・技術力の向上
のため蔵人を通年で雇う通年雇用も近年増えてきました。
サラリーマン同様の月給制で、
酒蔵の閑散期には
・設備のメンテナンス
・営業
・配達
など製造以外の仕事もやるのが特徴です。

どちらの働き方もメリット・デメリットはありますので、ご自身にあった働き方を選ぶようにしましょう。
酒蔵の求人の探し方3選

では実際に酒蔵の求人を探すとしたら
どのような方法があるでしょうか?

私が過去にもっとも苦労したのがココです…。
紹介するのは以下の3つです↓
①:ハローワーク

冒頭でもお伝えしたように
酒蔵の求人が大手新卒求人・転職サイトに求人が載ることはほぼありません。
載るとしても大手企業の一括新卒採用です。
もしくは大手企業の中途枠で一般職・営業職はたまに見かけますが、製造職となるとかなりレアです。
(この記事では中小企業、製造職に話をフォーカスします)
ハローワークのメリット
そこでまずチェックしておきたいのがハローワークです
中小の酒造メーカーの多くは
ハローワークに求人を掲載します。
酒蔵自体は全国各地に沢山あるので
ご自身が望む地域や待遇から検索できるのがメリットです。

私自身も、過去数回ハローワークから酒蔵とのご縁をいただきました。
ハローワークで求人を探すならこちら↓
ハローワークのデメリット
ハローワークを利用するデメリットですが、正直、検索ページが使いづらいです。
特にキーワード検索が微妙で
一番知りたい勤務地や待遇などを知るのにひと苦労。
絶妙にかゆい所に手が届きません。
そこで私の場合は
こちらの私設検索エンジンを利用しています↓
本家ハローワークのと比べると
キーワードでの絞り込みやすさが段違いです。
希望する
・勤務地
・報酬
・待遇
を比較しつつ求人を精査できるので非常におすすめです。

酒蔵の場合
「酒類」
「製造」
と検索するとヒットしますよ。
②:杜氏組合

全国各地には蔵人の技術交流・職業斡旋などを目的とした杜氏組合という組織があります。
現役の蔵人や杜氏が在籍しており
提携している酒蔵に欠員が出ると、組合を通じて職の斡旋を受けられる場合があります。
現在、日本酒造杜氏組合連合会には全国18の杜氏組合が所属しており、HPからお住まいに近い杜氏組合が探せます。
杜氏組合のメリット
酒蔵の中には、まず杜氏組合に募集をかけるところもまだまだあります。
ハローワークなどに公募される前の求人情報が得られ、鮮度のよい求人情報が得られるのがメリットです
また、実際の労働環境など雇用側には聞きづらいリアルな所も組合になら質問しやすく、志望先の精査に役立ちます。
杜氏組合のデメリット
ただし、組合ですので当然ながら会員費がかかります。
会員費は組合によって異なりますが
だいたい年間1~2万円程度が必要です。
講習会・技術者交流会などに参加できるメリットがあるものの、未経験者には組合加入はハードルが高いと言っていいでしょう。
できれば蔵人としての経験を積んでから加入するのがおすすめです。
③:SNS (X・Facebook・Instagramなど)

繰り返しになりますが、だいたいの酒蔵の募集人数は1~2人と少数です。
そのため、手っ取り早く興味のある人に届きやすいSNSを通じて求人が出てることもよくあります。
SNSのメリット
興味のある酒蔵を追いかけていると
ふとした時に求人情報が出てくることがあります。
【岩の井 蔵人・酒造り求人】
— 岩の井公式アカウント (@iwaseshuzo) September 30, 2020
岩の井は今シーズンの蔵人を募集しています。期間は11/1〜3/20当たりまで。
岩の井では酒造りの全ての工程を経験できます。
日本酒造りへの思いと、やる気があれば、経験・未経験は問いません。
興味ある方は詳細ご覧下さい👇👇👇https://t.co/VF2tRqyFux
特に、近年クラフトブリュワリー・どぶろく醸造所の新規開設が増えています。
お酒の製造だけでなく
既存の蔵人像にとらわれない求人が見つけやすいのも特徴です↓
来年から加工場やる予定で物件押さえてるんですが、誰か一緒にやりたい人いないっすかね?
— 岡住修兵|稲とアガベ|男鹿まち企画|代表 (@OkazumiSakehei) December 13, 2021
酒粕マヨネーズとフルーツバターとフルーツシロップの加工場。produced by てとてと。
地元の母さん方を従えてバリバリ作ったものを、全国のカッコ良いお店に届ける仕事。
画像は初期中の初期のイメージ。 pic.twitter.com/HafuKCbmiq
そういった求人では他業種からの経験も活かしやすいです。
SNSのデメリット
デメリットとしては
当たり前ですがSNSは求人を掲載するだけの場ではないので、いつも求人で溢れている訳ではありません。
運とタイミングの要素がかなり大きくなります。
それに、すべての酒蔵がSNSをやっている訳ではないので、情報量としては少なめなのは否めません。
また、ハローワークと杜氏組合では働きたい地域や待遇から求人を探せますが、SNSでは難しいです。
要するに
条件を絞って探すことができません。
「どうしても地元で働きたい」
などの譲れない条件が強いとマッチングは中々難しいでしょう。
おすすめの活用法

おすすめの求人の探し方を3つ紹介してきました。
それぞれにメリット・デメリットがあるんどえ実際に探す際には①~③の併用をおすすめします。
未経験者はハローワーク+SNS
未経験から蔵人を目指すならば
ハローワークを軸にSNSを補助的に活用するがおすすめです。
ハローワークの方がトライアル雇用を利用した未経験者可の場合が多く、敷居は低いイメージですよね。
そこに補助としてSNSをチェックして、希望に沿ったマッチングを目指しましょう。
経験者はハローワーク+杜氏組合
経験を積んだらハローワーク+杜氏組合の加入を検討してみましょう。
経験者になってからの方が杜氏組合に加入するメリットは大きくなります。
組合主催の講習会を通じて同業者との交流が生まれ、意見交換や顔ききが効くようになるからです。
働き手の高齢化によりどこの杜氏組合も会員が減少していますが、蔵人や酒蔵とのネットワークを構築するにはまだまだ有効な手段です。
どちらにしても、ハローワークはこまめにチェックしておきましょう。
なんだかんだで情報量は一番多いです。
まとめ:ベストマッチのために調べ方はとても重要

今回の内容をまとめると以下の通りです。
近年の日本酒ブームで蔵人という働き方が注目される機会は増えました。
ですが実際にやってみようと思っても、その門戸は狭く、まだまだ閉鎖的なものです。
偉そうな言いぐさですが
そのような現状は酒造業界としても人材の獲得機会を大きく逃すもので、決して好ましいことではありません。
酒蔵と志望者お互いにとってのベストマッチにつながるよう、今回の記事が蔵人の求人探しに役立てばうれしいです!
このサイトでは
食・発酵食に関する資格についても紹介しています。
興味のある方はぜひこちらもどうぞ↓